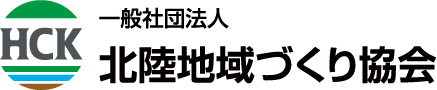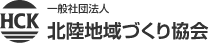今、時代は歴史的転換期を迎えています。行政改革、環境保全、グローバル化、情報化が進むとともに、私たちを取り巻く環境も大きく変化し、地域づくりにおいても、地方分権の進展とともに、各地域が主体となって地域の資源を活かし、創意・工夫を競う戦略が求められる時代へと変わろうとしています。
北陸地域においても、美しく豊かな自然環境、恵まれたロケーションを活かし、魅力ある地域づくりを進めていくための知恵・戦略が求められています。北陸地域づくり協会は、北陸地域に住む人々の英知や発想、研究を支援し地域の活性化に寄与することを目的に助成しています。
第30回 令和6年度能登半島地震を契機とした追加助成 募集のご案内
(一社)北陸地域づくり協会は、地域に住む人々の英知や発想を活かした多様な研究や活動を支援することにより地域の自立と活性化を促進する目的で、平成7 年度から「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業を行っています。
令和6 年1 月1 日に発生した令和6 年能登半島地震をはじめ、近年、各地で地震や豪雨による激甚災害が発生しています。災害に関する様々な課題を身近な問題として捉えた取り組みを促進するため、防災・減災、復興に特化した研究の追加助成を行います。
募集期間
令和6年5月20日(月)~令和6年7月19日(金)
【募集終了しました】
対象テーマ
【防災・減災、復興】
○自然災害の特性・災害リスクに関する研究
○災害に強い安全・安心な社会の構築に向けた取り組み
○災害時および平常時の防災支援活動
○被災地交流促進、災害の伝承、災害からの復興
○防災意識の普及・啓発・向上に向けた取り組み など
助成事業の概要
| 事業名 | 助成対象 | 助成金 | 助成数 | 審査 |
|---|---|---|---|---|
| ①技術開発支援事業 | 大学・企業・法人・任意団体・個人またはこれらの団体 | 20~50万円 (概算払 1/2まで) | 10 | 書類選考 |
| ②地域づくり研究事業 | ||||
| ③大学連携等による共同調査研究事業 | 大学または高専を含む2つ以上の機関 | 200~300万円 (概算払 1/2まで) | 2~4 | 書類選考 プレゼン テーション選考 |
※助成数は予定であり増減することがあります。
審査結果
○採択された事業については審査委員会終了後、1 週間以内に電子メール(申請書提出先アドレス)で連絡します。
○協会ホームページで公表します。
○審査の経過等に関する問合せには、一切応じませんのであらかじめご了承ください。
応募方法
募集要領・申請書をダウンロードし、よくご確認のうえご応募ください。
本事業でいう
北陸地域とは
新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県飛騨地域、福島県会津・南会津地域、山形県西置賜地域
問い合わせ先
一般社団法人 北陸地域づくり協会 企画事業部
E-mail:hr_kasseika@hokurikutei.or.jp
TEL:025-381-1160 FAX:025-383-1205
第29回(2024年度)研究助成事業
北陸地域づくり協会では、地域に住む人々の英知や発想を活かした多様な研究や活動を支援することにより地域の自立と活性化を促進する目的で、平成7年度から「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業を行っています。
第29回「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業は、令和5年11月20日から令和6年1月19日まで募集を行い、「技術開発支援事業」に8事業、「地域づくり研究事業」に38事業、「大学連携等による共同調査研究事業」に4事業の応募がありました。
令和6年3月4日、審査委員会を開催し、「技術開発支援事業」5事業、「地域づくり研究事業」10事業、「大学連携等による共同調査研究事業」2事業を選定・助成することを決定しました。


技術開発支援事業
- 耐久性設計のための北陸地方の気象履歴評価
-
新潟大学 工学部 教授 佐伯 竜彦
- 率先避難による避難誘発システムの広域大規模環境での評価
-
福井大学 学術研究院工学系部門 情報・メディア工学講座 准教授 川上 朋也
- R6能登半島地震における富山県沿岸域の避難時渋滞状況の把握と避難ルート検証
-
富山県立大学 工学部 環境社会基盤工学科 准教授 久加 朋子
- 実フィールドにおける全天候型UAVを用いた新しい気象観測手法の研究
-
富山県立大学 講師 吉見 和紘
- スマートフォンを用いた災害被災者支援システムに関する研究
-
新潟工科大学 電波応用研究室 准教授 沢田 健介
地域づくり支援事業
- 中学生による「発酵」の観光的な価値の拡充事業 ~越後・謙信SAKE祭りへの参画を通して~
-
上越教育大学附属中学校 教諭 仙田 健一
- E コマース(電子商取引)による地域活性化をめざす探究学習 /地域マルシェなどのEコマース化を通じて
-
新潟経営大学 経営情報学部 特任教授 西村 香介
- 白山市湊地区健康未来共創事業「SDGsと地域保健活動をつなぐ」-学生と地域住民の共創による地域活性化を目指して-
-
金城大学 公衆衛生看護学専攻科 講師 曽根 志穂
- 都市部からの”棚田の通い農”をもっと身近に!稲作シェアリングスポット「棚田ステーション」事業
-
(株)里山パブリックリレーションズ 代表取締役 星 裕方
- 地域インフラの役割、歴史を伝えよう -文化財登録からまちづくりへ
-
土木・環境しなの技術支援センター 理事長 古本 吉倫
- 砂防事業サポーターの育成
-
敬和学園大学 堀野研究室 堀野 亘求 (学生代表 清田 耀介)
- 持続的な社会基盤維持管理のための技術者育成事業
-
長岡工業高等専門学校 教授 井林 康
- 八十里越観光圏の共創と八十里越ハンドブックの作成・刊行 -新潟県央と福島県南会津に跨る観光資本の創造-
-
NPO法人 西潟為蔵会 理事長 弥久保 宏
- 福井地震に関するダークツーリズムの提案
-
福井工業高等専門学校 環境都市工学科 教授 吉田 雅穂
- 三方良し!建設企業紹介プラットフォームづくり
-
加茂商工会議所 会頭 木戸 信輔
大学連携等による共同調査研究事業
- 新潟県中越大震災から20年のアフター復興プロセス研究
-
(公社)中越防災安全推進機構 事務局長 諸橋 和行
- 農業・防災サイバーフィジカルシステムを用いた新教育プログラムの創出
-
信州大学 工学部 教授 小林 一樹
第29回(2024年度)研究助成事業 募集のご案内 【募集終了】
北陸地域づくり協会は、地域の自立と活性化を促進する目的で、平成7年度から「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業を行っています。
令和6年度も引き続き、地域に住む人々の英知や発想を活かした多様な研究や活動を支援します。皆様のご応募をお待ちしています。
募集期間
令和5年11月20日(月)~令和6年1月19日(金)
【募集終了しました】
対象テーマ
| A | 社会資本の維持管理 | メンテナンス技術、維持管理システム構築、老朽化対策、長寿命化、耐震化 など |
| B | 防災・減災 | 大規模・広域災害への備え、災害に強いまちづくり、防災教育、防災グッズ開発、コミュニテイの形成・活動 など |
| C | 地域振興・地域づくり | 地場産業再生、地域資源活用、観光振興、地域連携、インフラツーリズム、魅力・ブランド戦略、国際化(インバウンド含む)、住民参加、担い手づくり など |
| D | 持続可能な社会形成 | 環境、脱炭素社会、リサイクル、新技術の開発と活用や普及、i-ConstructionやDXの取り組み など |
助成事業の概要
| 事業名 | 助成対象 | 助成金 | 助成数 | 審査 |
|---|---|---|---|---|
| ①技術開発支援事業 | 大学・企業・法人・任意団体・個人またはこれらの団体 | 20~50万円 (概算払 1/2まで) | 15 | 書類選考 |
| ②地域づくり研究事業 | ||||
| ③大学連携等による共同調査研究事業 | 大学または高専を含む2つ以上の機関 | 200~300万円 (概算払 1/2まで) | 2 | 書類選考 プレゼン テーション選考 |
※助成数は予定であり増減することがあります。
審査結果
令和6年3月開催予定の「第28回助成対象事業報告会」で発表します。
応募方法
募集要領・申請書をダウンロードし、よくご確認のうえご応募ください。
本事業でいう
北陸地域とは
新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県飛騨地域、福島県会津・南会津地域、山形県西置賜地域
問い合わせ先
一般社団法人 北陸地域づくり協会 企画事業部
E-mail:hr_kasseika@hokurikutei.or.jp
TEL:025-381-1160 FAX:025-383-1205